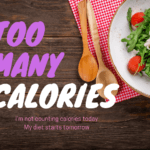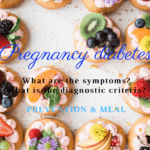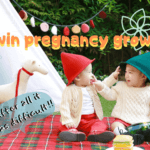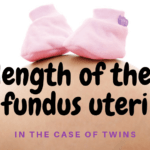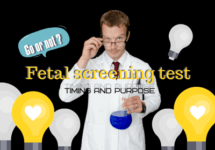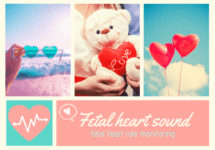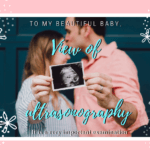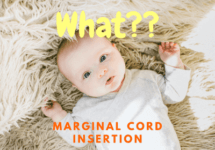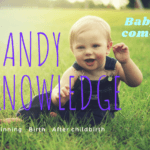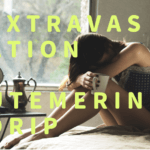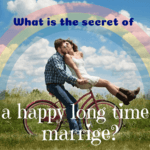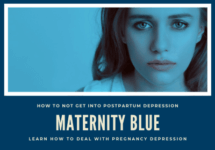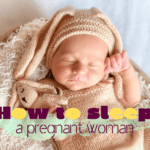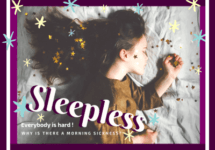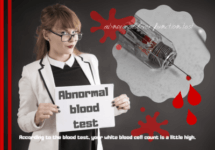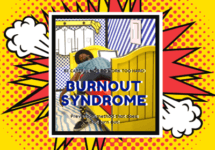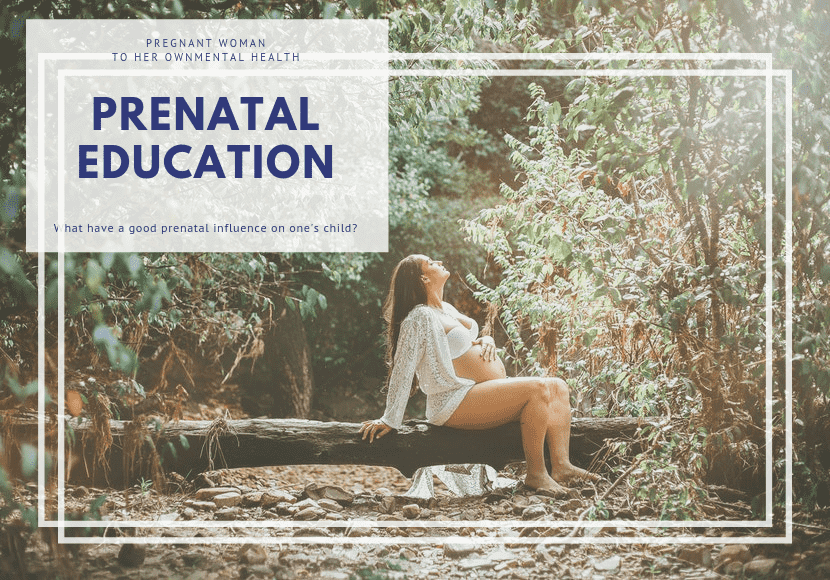
妊娠中の胎教で赤ちゃんの才能が開花できるとしたら?
「健康であればいい」と思うものの、親の欲目や期待は天井知らず。あわよくば天才児に…とは誰もが一度は期待するところです(^^;
仕事で忙しかったり、妊娠トラブルに見舞われたり、十分な胎教を行える余裕のあるマタニティライフを過ごせていない場合、「これで良いのかな?」と不安に思うこともありますよね。
そこで今回は胎教が胎児に与える影響や効果を調べました。
脳や聴覚などの神経発達を考慮した胎児の成長に合わる胎児教育の適切な時期や内容、胎教で一番効果がある方法、胎教に使えるアイテム、そして最後に私が実際に行ったゆるゆる胎教とその結果をまとめてあります。
赤ちゃんとの健康的なマタニティライフに役立てばと思います。
胎児教育の科学的根拠や効果はあるのか?
「胎教」と辞書を引くと、「妊婦が精神的安定に努めて、胎児によい影響を与えようとすること」と載っています。
その方法は様々で、胎教と聞いて思い浮かべるのは「クラシック音楽を聞かせる」「英語を聞かせる」などでしょうか。
「胎児教育」と聞くと、大層なことをしなくてはいけないように感じで、気後れしてしまうママや、熱心になりすぎて神経質になってしまうママも多いかと思います。
そこで、胎教には本当に効果があるのか検証してみたいと思います。
胎教の効果とは
胎教を行うことによって「何の効果を期待するか」で、その可否は変わってきます。
巷で言われている胎教の効果には、どのようなことが謳われているのかというと。。。
赤ちゃんの脳の発達に役立つ
- 言葉の理解や発語が早い
- 才能が伸びる(右脳系)
- 学習能力の高い子供になる
- 吸収力・理解力・記憶力がよくなる など
情緒が安定した子供になる
- 夜泣きをしない
- 人見知りをしない
- 表情が豊かになる
- いつも穏やかで笑顔になる など
すごいですね(笑)
まさに大人が期待している理想的な子どもです。
それ以外にも、胎教を行うことで「比較的安産になる」「親子・夫婦・家庭の絆が形成される」など、妊娠中・分娩時・出産後に好影響をあたえるとの説もありました。
果たして本当でしょうか?
以下は、実際に「胎児教育」をする専門施設を調査した結果になります。
胎教を行っている施設への調査報告では…
「妊娠管理における胎教」の論文では、全国規模で行っている胎児教育の施設の実態調査の報告がありました。
その結果は以下の通りです。
- 人間形成
- 天才児を産む
- 個性や心を育てる
- 感覚外知覚(右脳)能力開発
- 母性を育て胎内環境をよくする
- 胎児の情緒面と学習面を育てる
- 頭脳開発を目的とする胎内教育
- 天分(各自の能力)を育てる
➡ 意識の確立・学習能力・中枢神経などの「胎児に対する効果」を認める客観的な判断材料は無かった。
しかしながら、妊婦の生活態度・生活環境を整え、母性を育む「母親教育」という観点では一定の効果をあげていることが推測されるとありました。
また胎内記憶の調査では、新生児期に母親の主観で「赤ちゃんが喜んでいる(記憶がある)かどうか」を判断し、比較したところ、生後1~2ヶ月目では胎内記憶があることが観測されたそうです。
- 妊娠中に聞いた曲の方が反応が良い
- 妊娠後期に聞いた曲ほど高確率に反応がある
生後1カ月目と2カ月目のテストでは上記の結果になりましたが、生後6ヶ月目になるとその傾向は弱まり、はっきりとした反応差は無くなっていきました。
つまり、時間が経つほど胎内記憶は薄れていくということですね。
- 胎児と母体をつなぐ「へその緒」には神経がないので、母親の学習行動がダイレクトに胎児に伝わることはない
- 胎児は学習に必要な大脳新皮質が未発達なので、お腹の中でどの程度影響があるのかは定かではない
このようなことから、「天才児」「育てやすい子」を得るという効果を胎教に期待するのであれば、それを科学的に立証した報告は無いので、そういう意味では「胎教は効果がない」と言えます。
胎教は妊娠中や分娩中に影響を与える?
「胎教の効果に関する一考察」の論文では、胎教を積極的に行ったグループと、とくに行わなかったグループにわけて、妊娠中の変化や分娩時・出産後の影響についての研究報告がありました。
その結果は、以下の通りです。
- マイナートラブルや分娩時のトラブルの差はない
- 胎児の成長や出産直後の新生児の健康状態を表す指数の差はない
- 妊娠中の精神的な安定度は、胎教を行ったグループの方が高い
- 妊娠出産における満足度は、胎教を行ったグループの方が高い
このことから、「妊娠中・分娩時のトラブル」「胎児の健康」については効果は認められないと言えます。
しかし、胎教は妊娠中や分娩後に「精神的な充実」「自己肯定感」を得ることで、母親としての自尊心に繋がり、その後の育児にもよい影響が出ると推察されます。
胎教を行う意味と効果
胎教を行えば、100人中100人が「才能ある子」「夜泣きをしない子」になるかというと、まー冷静に考えてそんなわけは無いと分かっていただけたと思います(;^ω^)
そして、胎教は胎児のためというよりは、母親に良いということも。。。。
「胎教は効果がない」のではなくて、目的を間違わなければ「いいもの」であることには違いがないのです。
胎教の歴史
胎児教育の言葉の起源が、中国の古書「青史氏之期」であることをご存知の方は少ないのではないでしょうか。
もともとは、知識や徳望の優れた理想的な人物(=聖人君子)を目指す「思想教育」的なものだったそうです。
日本には医学書を通じて、胎教という考えが部分的に伝わりました。仏教が伝わったころと同時期というのだから、その歴史がわかりますね。
そして海外から伝来した他の思想や文化と同じように、長い歴史の中で日本に根付き、日本独自の胎教思想を発展させてきました。
- 妊娠中の慣習
- 食物・飲物の禁忌
- 家庭教育での諸注意 など
近代的な医療制度が始まり、西洋医学が浸透しつつあった明治に入ると、科学的根拠がないと言われるようになります。
妊娠中の食事についてはこちら。
現代における胎教のとらえ方
そして現代ではというと、科学はさらに進歩し、胎児の成長や発達についてより詳細に研究が重ねられるようになりました。
その結果、母親のストレスが胎児に悪影響を及ぼすことや、出産後の母親の安定した精神状態は子どもの脳を良い状態にしていくことなどが科学的に立証されたのです。
つまり赤ちゃんが健やかに育つには、「環境(母体)をよくすること」が大事で、胎教によってそれを得ようと考えられるようになりました。
➡ 適切な食事・運動・睡眠などの健康的な生活習慣
精神的リラックス
➡ 妊娠中、いかに楽しくストレスを溜めない生活をするか
いってしまえば、特別な教育などしなくても、ママが赤ちゃんを意識して行う「良い行動」は全て胎教であるとも言えますね^^
妊娠中のストレスによる悪影響についてはこちら。
胎児の成長と胎教を始める時期
もし胎教を少しでも胎児に伝えたいと考えると、まずは胎児の成長を知ることが必要です。
胎児に合わせた胎教の時期とはいつごろになるのでしょうか。
胎児の脳の成長
ヒトの脳は母体で受精した後、38週で形成されると言われています。その大まかな流れを見ていきましょう。
受精後18日
脳のもととなる「神経板」が形成される
受精後24日
成長すると脳と脊髄になる「神経管」が形成される
受精後30~50日
前脳、中脳、後脳が形成される
受精後2カ月
間脳、小脳が形成される
受精後4ヶ月
終脳が大きくなり、大脳としてのかたちを整えはじめる
受精後5カ月
しわが増え、神経細胞同士の連結と信号の伝達・処理機能など脳機能の整備が始まる
受精後6カ月
脳幹の発達が一定の水準に達するが、まだ実際に見えたり聞こえたりすることはない
受精後7ヶ月
大脳新皮質の形が出来上がり、脳幹の完成に近づき、音や光に対する反射が現れる
受精後8ヶ月
成人の脳と似た状態の脳が出来上がり、中耳が形成されて外界の音が聞こえようになり、光が脳に伝えられる
赤ちゃんの脳や神経は妊娠中、日々成長を重ねていきます。
胎児の脳は妊娠7~8ヶ月目には、外からの音や光に反応を示すようになるようです。
胎児の成長についてはこちら。
胎児の耳はいつできる?
ヒトの耳は、その奥の方から内耳・中耳・外耳の3つに分かれていいます。
耳が形成される大まかな流れは以下の通りです。
妊娠5~6週目
最初に耳らしい穴ができる
妊娠12週目
中耳が形成される
妊娠16週目
内耳と中耳が連絡する
妊娠21週目
外耳が形成される
妊娠29週~31週目
内耳と外耳の基本的な形態がほぼ完成する
胎児の耳の成長は妊娠7~8ヶ月目には、内耳と大脳を聴神経がつなぎ、音を感じとれるようになっていると考えられます。
胎児の成長についてはこちら。
胎児の聴覚はいつ頃から聞こえるようになる?
妊娠20週頃に胎児が音への反応を示したという事例や、妊娠26~29週の早産でも脳波で聴覚を検知できたという報告があります。
そのため、妊娠24週ころ(妊娠6ヶ月)には、音を聞き取れるまでに耳が発達しているとも考えられます。
しかし、脳とのネットワークが成熟するのは妊娠8ヶ月頃からで、その頃になると音の聞き分けなど「理解」できるようになるといわれています。
そして妊娠9ヶ月頃にはほぼ完成に近づいて、聴覚は生まれた後も2~3歳頃まで発達を続けます。
このようなことから、胎教は早くても妊娠6カ月から、実際は妊娠8カ月までに開始すれば十分と言えますね。
赤ちゃんの成長には個人差がありますし、ママの体調が落ち着いてからでも余裕で間に合うわけです。
胎児は音を覚えているか
ヘルシンキ大学による胎教の研究で、以下のような報告が紹介されていました。
実験は、胎生29週から誕生まで(中略)
生まれた後で、胎教に使った音を少し変化させ、脳波で反応を見る。
もし生まれる前に習った音を覚えていれば、その変化に気づくが、習っていない場合は聞き流すというわけだ。詳しい実験内容にはこれ以上深入りしないが、結論は予想通りで、間違いなく胎児期に聞いた言語様のパターンは記憶される。
ただ早とちりはいけない。今回の結果は、言語的パターンが脳内に記憶されることを示しただけで、それが役立つかどうかはわからない。(中略)
いずれにせよ、記憶可能である事が示されると、今後も様々な試みが続く可能性が予想できる。
赤ちゃんの感じる音
胎児の耳には、すべてが明瞭な「音」としては伝わってません。
お腹のなかで羊水を通して、振動を感じるように聞くことになるので、水に潜って聞く音に似ていると考えられています。
実際に胎内で録音された音は、高い音の成分がカットされ低い音になってるそうです。
そのため、細かい音の変化というよりは、大まかなリズム・メロディーなど、ある種の信号として赤ちゃんに届いていると言えますね。
また、胎児は20分おきに寝たり起きたりを繰り返しているので、親が音を聴かせた時点で聞いているかどうかは分からないので、胎動がある時に行うといいかもしれません。
胎児に感情はある?
最新の3Dや4Dの超音波を使い、胎児の行動や表情を観察し、脳や中枢神経の機能解析を行う胎児行動学の研究があります。
胎児をひとつの人格を持った人間と考えるものです。
- 妊娠24週くらいからは痛覚が発生する
- 6カ月で胎児は味覚を感じとり、羊水の味がわかる
- 一卵性双生児は胎内でお互いの存在を感じ、触りあう
- 胎児がストレスを感じると、腕を跳ね上げるように動かす
- 胎児は舌を出したり、あくびをしたり、指を口に含んだりと様々な表情をもつ
このように、お腹の中の赤ちゃんは様々な顔を見せてくれます。
胎内でストレスや心地よいと感じている時などに、胎児がどのような身体反応を示すかを研究する検討もされているそうです。
胎児に意識があるかはまだ分かっていませんが、いずれは「胎内が心地よい環境だと笑顔になる」「ストレスがある環境だと拒否反応を示す」といった胎児の感情が発見される日も来るかもしれません。
そうなると俄然「胎教による好影響」も期待できるようになりますね(*^^*)
超音波検査についてはこちら。
最適な胎教の方法とは?
胎児の成長や生態が分かったところで、では実際に胎教を行うとしたら、どのような内容がいいのか考えてみたいと思います。
前述の通りママがリラックスして安定することが第一なので、苦手なことや苦痛なことは行う必要はありません。
母親が心地よく感じているものは、胎児も心地よく感じていると考えましょう。
また、妊娠8カ月未満では、音楽や英語を聴くのは「胎児」というよりも「自分(母親)」と思った方がいいですね。
胎動を感じられる音楽とは?
妊娠中期の胎児に音楽を聞かせると、口を動かしてあたかもしゃべったり歌ったりしたいかのような反応を見せるそうだ。
ただし、お腹の外で音楽を鳴らしてあげるのではなく、ダイレクトに膣内スピーカーで聞かせてあげないと効果がないらしい。(中略)
研究者たちによれば、これは音楽によって胎児の言語を司る脳内経路が刺激された証拠だという。
すなわち音楽を聞いた胎児がコミュニケーションを図ろうとしているサインではないかと考えられるそうだ。(中略)
なお、これらの音楽はお腹の外から鳴らしても、腹部の分厚い壁に阻まれて胎児には届かないそう。
上記によると、膣内スピーカーで音楽を聞かせてあげたところ、胎児が口を動かしたり、ベロを突き出して反応したそうです。
以下は「胎児の反応が良かった胎教曲ランキング」の抜粋になります。
- モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
- スペインの混声合唱で歌われた「クリスマスキャロル」(実験が行われたのがスペインだったため?)
- イギリスのロックバンド、クイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」
その他に反応が良かった曲
- バッハ・プロコフィエフ・シュトラウスなどのメジャーなクラシック
- アフリカの伝統的なドラムビート
- インドのお経
- アメリカのディスコグループ、ヴィレッジ・ピープルの「Y.M.C.A.」
上記の選曲を聞いて、ママやパパがストレスをためるのであれば逆効果なので注意しましょう^^;
またBGM的に音楽を聴かせる胎教は手軽ですが、どこまで胎児に聞こえているかは分かりません。
自分で胎教音楽が作れちゃう!
スマホの専用アプリを使用して、赤ちゃんの心拍数を自宅で計測、保存、履歴管理ができる商品です。
こ知らを使うと、ママの心拍音と、赤ちゃんに聞かせたい音楽をミキシングして、オリジナルの胎教音楽や心臓の音の子守唄を作成できます。
妊娠中の健康管理(測定情報の分析、心拍数、規則度、心臓年齢、ストレス指数、アルコール敏感度、カフェイン敏感度、食事療法、運動情報)のサポート機能も充実している高性能グッツになります。
普通の胎教音楽では物足りない方におすすめ!
クラシックやモーツァルトが胎教にいいと言われる理由
音楽セラピーというものもあるようで、音楽は脳や心理に深く働きかけるものであり、その効果が科学的に証明されているそうです。
クラシック音楽が良いと言われているのには以下のような理由があります。
音楽は「A10神経」を刺激するとされ、それによりドーパミンが分泌されて気分が高揚し、やる気を出すことができる
セロトニンが分泌されるから
クラシックのようにロジカルに組み立てられた音楽は、脳を適度に刺激し、ドーパミン・セロトニン・アセチルコリンといった「幸せホルモン」と呼ばれる神経伝達物質を分泌させることにつながる
1/fゆらぎを含むから
モーツァルトの曲には「1/fゆらぎ」とよばれる自然音に含まれる音のゆらぎ(副交感神経を刺激し、リラックスする音域)が含まれるため、自然音を聴いているようなリラックスした気分になる
このように、クラシックは「ヒトの脳波によい」「α波が出る」とされる曲が多いため、母親のリラックスタイムに最適というわけです。
しかし、どの音楽で精神的な安定が得られるかは、人によって好みは分かれるので、自分の好きな曲で充分と思われます。
ちなみに言うと私は音楽に全く興味がないので、無音で過ごしました(笑)
胎教に良いクラシックはこちら!

モーツァルト編は一番α波が出ているのか、リラックスして心地よく眠くなります・・。
α波が出ている時は、ホルモンの分泌が盛んで赤ちゃんの脳が著しく成長するそうです。
やはり胎教にはモーツァルトと言われる理由が分かりました。
オルゴール編は聴いていると、本当に幸せな気分になります。どれもお勧めです。
家ではもちろん、車内でも聴けるように、HDDにも落しました。
ドライブ中に聴くクラシックもいいものですね。
一緒に聴いていた夫も癒されるねーと満足そうでした。
胎教にだけでなく、出産後もずっと子供と聴きたいです。
5枚もありそれぞれ違うテイストなので、いろいろなシーンで使い分けて楽しみたいです。
一番いいのは胎児に話しかけること
英語や音楽を聞くのは、実際は「母親の耳」です。
しかし早い段階から直接「胎児の耳」に届く音、それはママの声になります。外からの声は濁ってほとんど伝わらない時期から、ママの声だけは身体を通して聞こえるのだそうです。
母親が話しはじめると胎児の心拍数が上がるというデータもあるように、母親の声は胎児にとって特別な音になります。
胎児に優しく語り掛ける言葉は、身体に響いて胎児まで伝わります。
生まれたての赤ちゃんは、お腹の中で聴いていた声を記憶しています。
また、ヒトの脳は「繰り返し触れているもの」に関心を示すようにできています。
たくさん話しかけてあげることで、赤ちゃんにとってママやパパの声は安心できる「特別なもの」になっているはずです。
胎児の語りかけにはこれ!

最初は反応がなかったですが、少しずつ声に反応して動くようになり、すごく嬉しいです!!
買ってよかったです!
胎教に絵本がいいのはママが読むから?
胎教に良いとされている絵本の読み聞かせ。これも「母親の声」効果が期待できます。
産まれてきてからも確実に絵本は読むようになると思うので、早いうちに読んであげたい絵本を選んで読み聞かせるのもおすすめです。
英語も音楽も、ただ聴かせるのではなくて、ママが実際に声に出して読んだり歌うと、直接赤ちゃんまで届くことが出来るかもしれませんね^^
胎教で使える絵本が無料で印刷できる
あかえほ
「あかえほ」は赤ちゃん向けの創作絵本サイトです。パラパラめくれるウェブ絵本、印刷できるPDF絵本をご提供しています。読み聞かせを気軽に始めたい方へ。
こちらは無料で閲覧・印刷できる絵本のサイトになります。
かわいらしく種類も豊富なので、プレママにぴったりですね^^
妊娠中におすすめのアプリやグッツはこちら。
私が行った胎教とその結果
そんなわけで、もともと面倒くさがりで、合理主義&効率主義な私は、特別なことは何もしていませんσ(^_^;)
しかし、広義の意味での胎教であれば、以下のようなことを心がけました。
お腹をなでる、話しかける
管理入院は大部屋のため、音楽や絵本の読み聞かせ、大っぴらに双子に話しかけるようなことはできませんでした。
ただベットから動くことが出来ない代わりに、胎動を丁寧に感じ取ることが出来たので、胎動があった時はお腹をなでたりタッチしたり、できるだけ反応を返すようにしていました。
(キックゲームは根気が続かず行わなかったです。笑)
またニックネームも恥ずかしくて、たいてい「ツインズ」「おにーちゃん」「おとうとくん」といった感じで呼んでいました。
シャワーの時間は完全に一人になるので、その間の30分はできるだけ語りかけを行うようにしていたくらいですね。
管理入院中のお風呂事情についてはこちら。
胎児教育は母親のリラックスが一番
妊婦が不安になるとアドレナリンの分泌が増え、胎盤への血液量が減るという報告があります。
そういった面でも妊婦のストレスは胎教にもよくありません。
もともと管理入院でストレスMAXだったため、ストレスを完全になくなることは難しかったですが、毎週末に主人がお見舞いにきてくれたので、夫婦仲は良好でした。
差し入れやらマッサージやらで労ってくれ、愚痴につきあってくれていたので、感謝しかありません。
パートナーと仲良くするだけでも、妊娠中のママの不安は軽減します。
例えば旦那さまが奥さまの体調や環境に配慮し、「安心感・心地よさ」をたくさん感じる毎日を過ごせるように協力することも、立派な胎教ではないでしょうか。
夫婦関係についてはこちら。
妊婦の幸せは赤ちゃんの幸せ
悲しみ・怒り・不安・衝撃…
- パートナーやご家族に、妊娠中で情緒不安定な事を伝えて、無駄な喧嘩を回避する
- あまりに大きな音、騒音、振動で、母体が驚いたり不快になるような場所にはいかない
- 妊娠中にできるストレス解消法を見つける
気分が落ち込んだり、イライラしたり、気持ちが不安定になっても、「ホルモンのせい! 赤ちゃんも分かってくれる!」と開き直って、引きずらないようにすることも必要です。
妊娠中の気分の落ち込みについてはこちら。
食事や睡眠などの生活習慣
夜更かしや昼夜逆転生活は、自律神経を乱し、ホルモンバランスを崩します。すると身体全体に変調をきたし、精神的にも追い詰められ、ストレスが蓄積する悪循環を引き起こします。
胎児は自分のペースで寝たり起きたりを繰り返しているので、「胎児の睡眠の質」に直接の影響を及ぼすことはありませんが、母体の心身の不調が胎児に悪い刺激を与えることを避けなくてはいけません。
そういう意味では管理入院中は規則正しい生活ができていたと思います。
妊娠中の睡眠についてはこちら。
ゆるゆる胎教の結果
このような感じで、胎教らしい胎教を行ってこなかったのですが、一番の収穫は「早産にならなかったこと」でしょうか( *´艸`)
妊娠17wで子宮頸管2.4㎝を切ってから、約20週間の安静生活の中で、まさか双子で正期産までお腹の中に留めておけるとは、家族の誰も予想していませんでした。
妊娠中の願いは、ただただ「無事に産まれてきてくれること」。それ以上は何も望んでいませんでした。
そのため、唯一行っていたシャワーでの語りかけは「まだ出てきちゃだめよーあと〇日はだめよー」と毎日カウントダウンしながら言い聞かせていました。
それが功を奏したのか、子宮頸管長は低空飛行を続けながらも、かろうじて双子を支えてくれたのです。
だんだんと正期産に近づくと余裕が出てきた
計画帝王切開の予定日の1日前に生まれると、誕生日がゾロ目になって覚えやすいので「どうせなら前日に生まれたらいいのにな~」と双子に言っていたら、本当に前日に緊急帝王切開になりました(笑)
しかも本来の予定日に切り替わる直前の「23:58」と「23:59」に生まれるという奇跡? の滑り込み出産でした。
まさかまさかで、希望通りの誕生日になって結果として大満足!(*´▽`*)
産後からは、手がかかる「育児難易度が高め」な双子で、飛びぬけて「スゴイ!」という才能は今の所ありませんが、(親バカ補正で)優しく元気で可愛い子に育っています。
胎教の結果を考える
私が妊娠中にトラブルのない「普通の妊婦さん」であれば、もっと色々とチャレンジしたかもしれませんが、今振り返っても特に後悔はありません。
まとめ
- 胎教の歴史は古いが、胎児の成長に直接的な効果を証明する報告はない
- 胎教には母親教育の側面があり、その点は高い効果が期待できる
- 妊娠中に赤ちゃんを想う気持ちを育むことで、母親の自覚や自尊心が生まれ、育児においてもプラスの効果が現れる